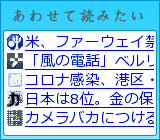| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ちょこっと思いつきをメモしときます。
昨日行われた「福知山支部 実践消防訓練」を終えて、感じた事ですが、当然の如く、すんなりと火点を落とすのが出来映えとしては良いのでしょう。
しかしながら、アクシデントに見舞われた時の対処が出来てこその「実践」だと思われます。
恥ずかしながら、私の分団はイージーミスをおかしました。
これが 火災現場 だったら と思うと ゾッ とします。
もちろん、火災現場ですと、昨日の訓練の数倍のプレッシャーが掛かるでしょうから、人的なミスが出てくるのは明らかです。
当然、「訓練」はそういった事柄を無くす為に行われるものだと考えれます。
と云うことは、我が分団のミスは偶然に起こったものでは無く、起こるべくして起こったものだと云えます。
・・・・確率的にはかなり低いと思われますが・・・・
ようするに、普段の訓練では「起こるはずが無い」って見過ごしている「物」こそ掘り起こして潰していかなくてはならないのです。
大会の前に配布される「要綱・要領」etcを追いかけていてはミスの根源を絶ちきる事は出来ないんでしょうねぇ。
もちろん、「要綱・要領」に沿った訓練も必要ですが、今回の「実践消防訓練」に対しては、もっと我々の活動の本質を考えた訓練が必要だった痛感しています。
・・・例えば、現場へ行く途中でパンクした・小型ポンプのバッテリーがあがっていた・真空がとれなかった・など定期点検を行っていれば、「そんなこと起こらないっすよ!」 ・・・みたいな事柄を「・・そうなったらどうする」って云うのを考えておかないと、”その時”に指揮者はどうする事も出来なくなっちゃいますよねぇ。
先輩方は「臨機応変」って良く云ってましたが、臨機応変に対処するって難しい事ですよ。
やはり、いろんな事を想定し、それを訓練で実施して「経験」って引き出しを多く持っていてこその「臨機応変」だと思います。
今回は、私の訓練計画のミスでした。
出場して戴きました団員の方々、申し訳ないです。